マンションのフロントマンに必須の資格と言われる「管理業務主任者」資格ですが、合格率は20%前後と、なかなか厳しい数字となっています。
資格がなければ、独占業務である「管理事務報告」や「重要事項説明」を行うことができないが、勉強時間がなかなか捻出できない・・という方も多くいるのではないでしょうか。
この記事では、実際に1か月の勉強で管理業務主任者試験に合格した実体験をもとに、最短で合格するためのスケジュールを伝授します!
①11月1週目
速習テキストの「まとめ」部分を書き出し!
私が使用していたテキストには、小単元ごとに「出るとこまとめ」というページがありました。
テキストの全部を最初から読んでも、なかなか頭には入っていきません。そこで、試験に出やすい箇所をまとめた部分だけを書き出して、少しずつ頭に入れていきます。
部分的な書き出しとはいっても、80以上のページを書き写しますので、土日それぞれ12時間程度、平日1~2時間程度の時間がかかります。
加えて、私の場合は利き手が腱鞘炎一歩手前くらいまでになりましたので、湿布をご用意されることをお勧めいたします・・・。
書き写していくと、「おや?これは前にも書いたような気が・・」と既視感のある単元がいくつか出てきます。ここが、試験に出やすいポイントなんです。民法での決まりと区分所有法での決まりの相違点や、区分所有法での決まりと標準管理規約での書き方の相違点が試験でよく問われます。
既視感のある単元に出会ったら、一度前のページへ戻り、相違点を比べてみることをお勧めいたします。
②11月2週目
1週目に書き写したものを振り返りつつ、「一問一答」の問題集を数回繰り返しましょう。
土日それぞれ10時間ずつ程度、平日は通勤時間などの隙間時間でかまいません。
一問一答を何時間も繰り返すと、かなりの脳疲労が表れます。私のおすすめは、ブドウ糖をこまめに摂取することです。試験前によく食べていたのが、「ラムネ」です。
おすすめは、少し炭酸みのあるシュワっとしたこちらのラムネ!少しですが、刺激になり、気分転換になります(^^)

令和5年・6年と、本試験にかなりの「個数問題」が出題されるようになりました。
「個数問題」とは、「正しいもの・誤ったものはいくつあるか」という形式の問題です。通常の、4問の中から正しいもの・誤ったものを探し出すのとは違い、4問すべての正否が問われる問題であるため、正解率が下がりやすくなります。
この個数問題の突破力を養うために必要なのが、「一問一答」に慣れること!
極端な話ですが、50問の試験問題のすべてが個数問題であった場合、それはもう「200問試験」であるのと同じなんですね。そして、難易度がカンストしていると見受けられるこれからの管理業務主任者試験では、個数問題の比率がどんどん上がっていくことが予想されます。
試験で正しい正解を導くのはもちろんのこと、膨大な問題数への慣れが必要不可欠になってきます。
③11月3週目
過去問に取り掛かりましょう。目安は10年分ですが、民法など大きく改正された分野は、改正後のものを繰り返し解くほうが効果的です。
土日でそれぞれ3回分、平日1回分ずつを目標に頑張りましょう。
過去問は、印刷して当日と同じように50問一気に解くことをお勧めします。当日は、どれだけ自信があっても、なんなら自信があるだけ、緊張して手が震えます。私がそうでした。ですので、なるべく当日と同じ状況に慣れることが大切になってきます。
過去問を解いている最中は、分からない問題の解答の横に「?」を必ず書くようにしていました。また、誤っている個所には、下線を引いて「×」をつけ、間違った知識を覚えたり、勘で解いた問題をそのままにしてしまうことがないようにしましょう。
また、解説を見て分かった気にならず、間違えた問題は必ずテキストで再読しましょう。この段階では、①で作成したまとめではなく、テキストを再読することを強く勧めます。試験で明暗を分けるのは、本当に細かい知識であったりするので、そこが網羅されないと、合格した後の業務で躓くことになり、本末転倒です。同じところを何回も読むことになったとしても、テキストを再読しましょう。
この方法で過去問を解いていくと、大体1回分に3時間ほどかかり、非常に疲れます。ラムネ休憩を忘れずにとってくださいね(笑)
④11月4週目
土日それぞれ10時間程度、平日30分から1時間程度を使って、過去5年分の過去問を再度解きなおしましょう。間違えた問題や、勘で解いた問題については、③と同じ方法で頭に入れていきましょう。
また、隙間時間で一問一答を繰り返し行い、苦手分野を克服することに努めましょう。
私はこの頃になると、脳みそが完全にオーバーヒート状態になっていました。テキストを読んでも、字の上を目が滑っているだけのような状態になっていました。どうにか覚えなければ・・と思い、試してみたのが「音読」です。これがなかなか良かったです!テキストの単元を音読すると、読むだけではなかなか頭に入ってこない知識が、強制的に頭に入っていく感覚があります。書き写すには長い文章などは、音読してみることをお勧めします。
本屋で販売している「模試」についても、この頃に解いてみることをお勧めします。購入する際は、テキストと同じ出版社のものを購入されるのがよいかと思います。問題文のちょっとしたニュアンスに各社の色が出るため、テキストと違う出版社のものを使用すると、解説を読んでもわかりづらい時があるためです。
私の場合は、3回分の模試を行い、その中から数問が本試験に出題されました。数問で結果が分かれる試験ですから、たった数問とはいえ、侮れません。
⭐いよいよ試験当日――・・・!
試験は、勉強すればするほど、不安になるものです。
特に、試験問題の最初が、受験瀬の多くが苦手とする「民法」であるため、難しい問題が1問目に出てくると、さらに焦ってしまいます。
試験は2時間もありますから、落ち着いて、分からない問題は両手があったまってから、じっくり考えるぐらいで大丈夫です。
自分を信じて、試験に挑みましょう!
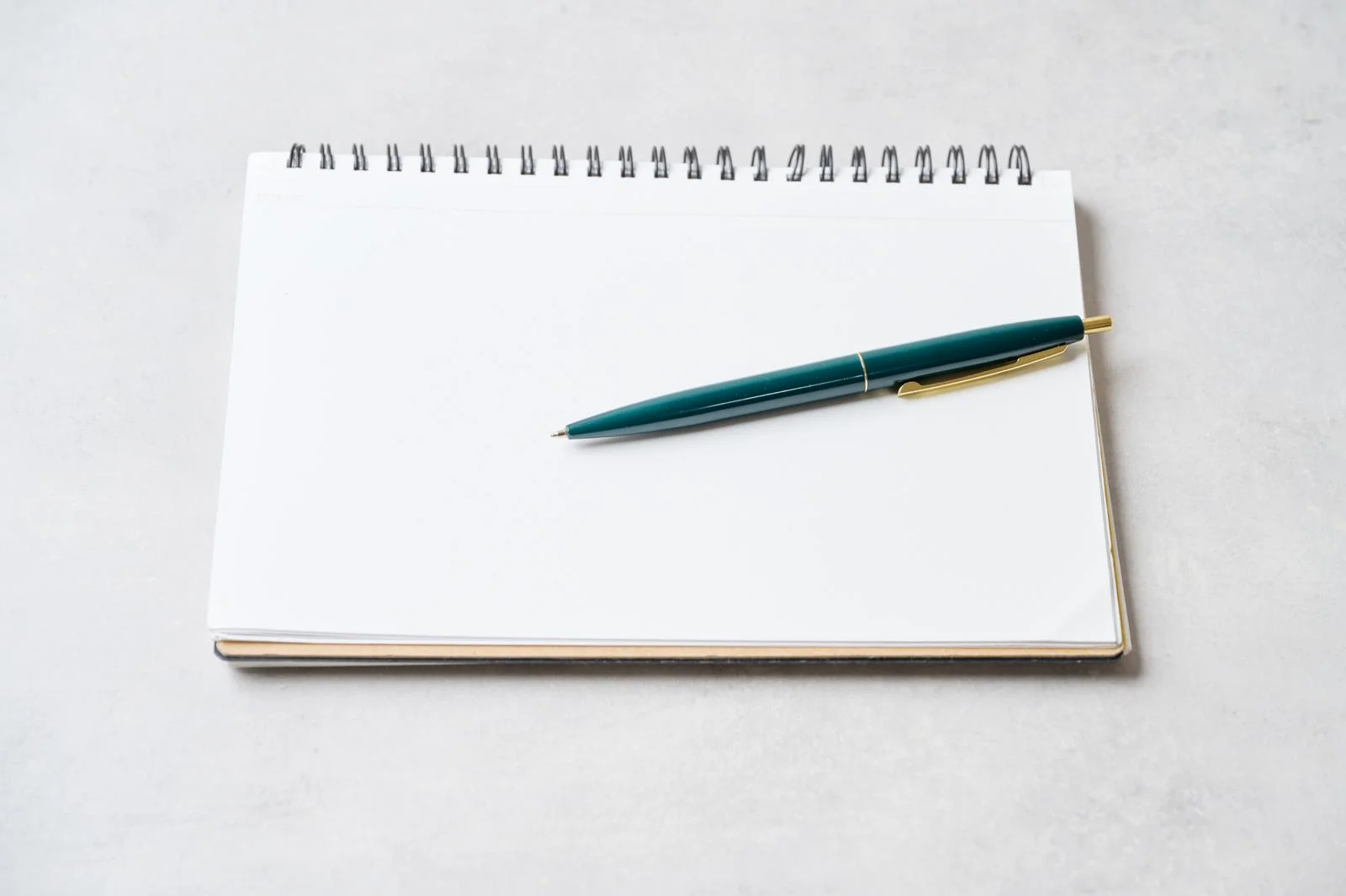

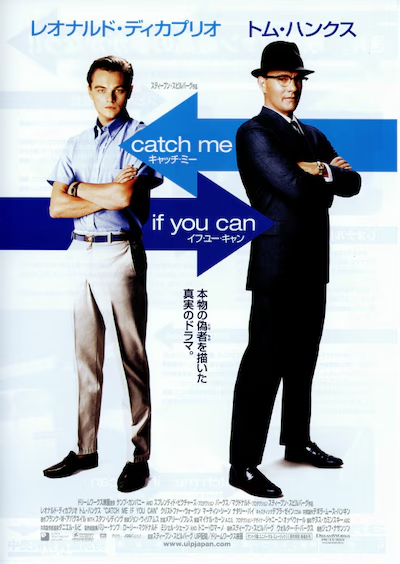
コメント